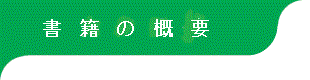要旨:著者 本書の序文より
現代中国人文学を考える ―コウモリのぶらさがり位置―
1 はじめに
中国とは、いまやまさに巨大な謎だ。世界における政治的発言力は、従来から米ロにひけをとら
なかったが、21世紀に入ってからの経済発展は驚異的であり、とくに金融危機のさなか経済的存在
感は、アメリカをしのぐ。GDPで世界トップの位置を占めるのも,夢ではなくそう遠くないことであ
ろう。一方で,2008年には国民一人当たりのGDPも3000ドルを越えたものの、あいかわらず「発展途
上国」並み(中南米エクアドル、ペルーは2006、2007年に越えている)であることには変わりない。
この背景には、沿岸都市部の富裕層から山間部の貧しい農民にいたる階層的格差の激しさがあるこ
とを忘れてはなるまい。
だがそのような現実が形成されてきたことには,さまざまな歴史的、社会的要因があるだろう。そし
てその現実のなかに実際に生きる人々の営みには、統計的数字によっては明らかにされない,具体的
で人間的な悩みと痛みを抱えているのである。学術的知性そのものが,実用的な社会科学を中心とし
ていく最近の趨勢には,一定の社会的必要と関心が反映している。しかし社会背景も含めて、依然と
して不透明である「他者」に対して、少しでも相互理解を目指し,「他者」との対話を試みようとす
るなら、文化的歴史的理解が,要するに人文学的関心が不可欠になるであろう。「他者」の精神構造
と歴史的文化的経緯を知らずして、現在または近年の動きだけで論ずること,、とても危険なことだ
から。本書の目標は,中国(アジアや東北アジアを含めた)という不透明な「他者」を直接解き明か
すことではないが、そのための一里塚として,今までの日本の近現代中国に関する人文学(歴史・思
想・文学)を検討し,その軌跡を追いながら、現在の課題と今後への展望を考えてみようとするもの
である。自然,それは私たちの中国や世界に対する見方を浮き彫りにするし、問題に対する対処のあ
り方も検討の対象となる。その場合,私たちが無意識に、当たり前だと前提としている知識も、もう
一度検討され直さなければならないことになるだろう。すぐのちに述べるが,中国は私たち日本の社
会と意識にとって、ある種の「鏡」のような機能ももってしまっているからでもある。
2 優越感と劣等感
さてまず、中国という対象が「謎」めいていることのひとつには、学問的にも、従来から矛盾する対
立的な理解が並存してきたことであろう。斯波義信は「とどのつまり中国は「都市の国」であり、同
時に「農村の国」であるという二律背反する不思議な社会になってしまう」と述べた。一方では「自
給的なからに閉じこもる農村集落がはてしなく分布する」とし、「タテ社会の統制がストレートに社
会を底までつらぬいたと考える」。「他方で二千余年の行政都市網の存続というまぎれもない事実に
よって、県城の生成分布こそが都市化の常数であり、県城を介する大伝統の拡散普及に都市史の領域
をみようとする見解がある」と 。
こうした矛盾した見解は、農村に限っても「閉鎖的で自立的農村」というイメージと、「地域のネッ
トワークに組み込まれ、一旦「騒ぎ」が生じると、一挙に連携する」というイメージとして、対立し
ながら並存してきた。また現在ですら、王朝体制以来の統治システムを中国共産党が引き継ぐ形で(
コミュニズムというイメージとともに)「専制独裁」という固定観念が、日本を含めた西欧社会では
強い。しかし本当の「独裁」であれば、一般庶民は、画一的で従順であって然るべきなのに、一人ひ
とりの中国人は、個性的で自己主張が強いという声もしばしば聞こえてくる。にもかかわらず、外部
に敵がいるときの「団結力」は強いという印象もあいかわらず根強い。
こうした対中国観は単に知的な理解にとどまらず、実体のつかめない不安感とともに、メディアや実
体験を通して、日本の社会に近年浸透してきていると言えよう。この間、日本の若い人たちの中国に
対する眼差しも、大きく変化してきた。西川長夫が1992、93年に調査したアンケートでは、中国は「
好きな国」の第4位と2位にあったし、2000年には第4位にとどまっていたが、同年では「嫌いな国」
でも第4位になった 。私がこの数年行った、大学生を対象としたアンケートでは,「好きな国」への
投票はごく少数で、「嫌いな国」では第3位が定位置となっている。この10年から20年間のいきさつ
といえば、中国で開かれたサッカーアジアカップにおける日の丸・君が代に対するブーイングや靖国
問題、総じて言えば、新しいナショナリズムの問題と「歴史認識問題」が、まずは考えられよう。こ
れらの問題については、多くの議論がすでにあるのでここでは詳しく触れないこととする。ただ本書
では、「歴史認識」の章を立てて、中国人との文献を通した対話や直接の対話を通して、私の個人的
考えを述べておくことにした。
ところで、中国に対する嫌悪感がいままでよりも強くなった(といっても、好感度は漸減しているも
のの、好悪ほぼあい半ばである)背景は、「反日感情」への直接的な反発だけではなかろう。冒頭述
べたような、中国の世界における政治的、経済的プレゼンスの増大に、ある種漠然とした脅威を覚え
ているというのが、日本の世論の実情ではなかろうか。このことには、実は遡れば長い屈折した歴史
がある。中国を対象とするとき、私たちが気をつけねばならないのは、無意識に日本の歴史的文化的
文脈を受け継いでしまうことだろう。近世まで日本の物理的な、精神的な何かが、自らをうちたてよ
うとするとき、つねに意識されたのが中国であった。本居宣長の国学が「唐物」と自らを弁別すると
ころから始まったことは、よく知られたことだろう。本書「地域研究」の章において、「アジア」に
関する議論を短文にまとめたが、そもそも「亜細亜」という概念自体が、中国は何ら中心ではなく、
世界の諸国のひとつにすぎないことの願望確認の反映として、江戸時代に取り入れられたのであった。
私は、あらたな「アジア」イメージを構想したいと願う者のひとりだが、そうした歴史的文脈は忘れ
られてはならない。
日清戦争以降、中国に対する差別感、侮蔑感は広まり、近代化を達成できない、遅れた中国というイ
メージが定着した。「アジア」の地域概念に中国を取り込んだ後、今度は「脱亜入欧」によって、自
らを「アジア」から区別したのである。日本人の「優秀性」を他のアジア人と区別する発想が強まっ
たのであった。近世近代の日本を見ていくと、並木頼壽の指摘するように「自らの日本がアジアに属
するのか、また、アジアのどこに属するのかという点で、日本人のアジア観には深刻な矛盾や分裂が
あった」 のである。
アジア・太平洋戦争の敗戦ののちも、一般には敗れたのはアメリカに対してであって、中国にも敗れ
たという意識は希薄であった。しかし毛沢東による中国革命の目覚しい変革については、少なからぬ
知識人、学生が注目し始める。むろん、戦前のように中国に滞在し、身をもって現地を知ることがで
きない状態にあった人びとにとって、それを過大に、理想的に受けとめたことは、やむを得なかった
だろう。ちょうどそれは、近世以前の日本の知識人が、書籍を通じて中国に憧憬を抱いたのと、いく
ぶん似ている。そのことは、1966年文化大革命の勃発と10年後の収束において最も顕著に現れた。収
束の後、その被害の実情が明らかにされるにつれて、当初、先進的実験を行っている、進んだ社会主
義国中国というイメージが理想化された反動として、王朝体制とあまり変わらない封建的で遅れた社
会というイメージが強調された。日本の中国観には、近世まで、圧倒的な中国文化からの影響に対す
る、あこがれとコンプレックスつまり劣等感があり、明治以降、これを裏返しにするような、侮蔑と
怖れがないまぜになった優越感の感覚があったといえよう。そしてそれは、現在までもコインの表裏
のように、私たちの観念にひそかに住み着いているかもしれないのだ。
先の並木はこう述べている。「中国は、その存在が歴史的に巨大であり、近代に従属的な位置におか
れてもなお巨大な存在感を有していただけに、近代の日本人にとっては一種のこえがたい圧迫感をも
たらす存在でありつづけた。そのため、近代の日本人のあいだには、中国をできるだけ小さなものに
したいという願いがぬきがたくしみついていたようである」 。これは現在においても、有効なことば
であろう。中国を見る眼差しが、実は日本人自身を映す「鏡」であるというのは,そうした意味におい
てである。(以下略)
書評:タイトル 氏名:
|